「風通しがいい」は本当に理想の職場なのか
2021.12.9(木)
フリーライター 西岡一紀
「社長と何でも話せる」のはいいことか?
理想の職場像として、若手や社歴の浅い社員でも経営陣と直接意見などのやり取りができる「風通しのよさ」をあげる人は多いと思います。しかし、本当にそうでしょうか?経営者の中には、敢えて「風通しを悪くしている」というケースもあるようです。
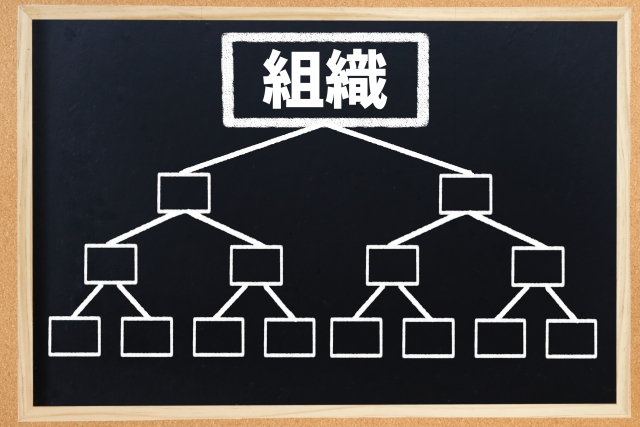
ある介護事業者はA市で2ヵ所の高齢者住宅を運営していました。社長はどちらかのホームにいることが多かったので、スタッフも何かあれば社長に直接報告したり相談をしたりできる、いわゆる「風通しのいい職場」になっていました。
さて、この会社はB市に新たに高齢者住宅を開設しました。また、その後もB市での新規開設案件を複数抱えていました。こうなると社長はA市のホームにばかりいるわけにはいきません。そこで事業拡大を機にA市・B市それぞれに統括マネージャーを置くことにしました。それと同時に社長はスタッフが社長に直接報告や相談をすること禁止しました。スタッフと一緒に食事をすることも止めたそうです。
この理由について社長は「私に直接連絡や相談ができる体制のままだと、統括マネージャーがいても誰も彼に連絡・相談をしないでしょう。組織がある程度の規模になったら経営陣と現場を繋ぐ役割を果たす人が絶対に必要になります。その役割がしっかり機能するためには、私が現場から遠い存在になる必要がありました」と語ります。
「自分は特別な存在」と職員が勘違い
もう一つ同じようなケースを紹介します。ある社会福祉法人が運営する特養では、離職率の高さに悩まされていました。そこで民間介護事業会社での勤務経験が豊富な人を理事兼施設長として招聘して立て直しを図ることにしました。この新理事がまず取り組んだのは、やはり「スタッフから施設長への直接的な連絡・報告・相談の禁止」でした。
理事が施設長を兼ねていることからもわかるように、この法人は他法人に比べると施設長がかなり経営陣に近い存在といえます。組織もかなりかっちりしたピラミッド型をしていました。しかし、前任の理事兼施設長は「風通しのいい職場」を目指し、スタッフが直接連絡してくることを好みました。とはいうものの、スタッフ全員が性格的に理事と気さくに話ができるとは限りません。中には気後れして話せないスタッフもいます。その結果として、性格的にものおじせずに理事と気軽に話ができていたスタッフたちが「自分は理事とどんなことでも話せる特別な存在だ」と勘違いし、暴走を始めてしまいました。彼らがリーダーなどの意見・指導に従わず、職場の中で勝手な振る舞いをすることに嫌気がさした人が多かったことが、高い離職率の原因だったのです。
このように「風通しのいい職場」は、ともすると「声の大きいスタッフ」の意見が優先されてしまう危険性をはらんでいます。もちろん社長などの上に立つ人が「裸の王様」になってしまってはいけませんが、ある程度は「遠い存在」になることが、指揮・命令系統がしっかり機能する組織づくりのためには必要なのではないでしょうか。

西岡一紀(Nishioka Kazunori)
フリーライター
1998年に不動産業界紙で記者活動を開始。
2006年、介護業界向け経営情報紙の創刊に携わり、発行人・編集長となる。
2019年9月退社しフリーに。現在は、大阪を拠点に介護業界を中心に活動中。
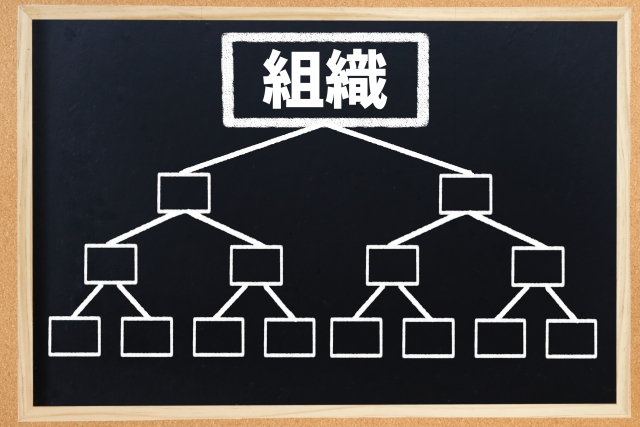
 西岡一紀(Nishioka Kazunori)
西岡一紀(Nishioka Kazunori)